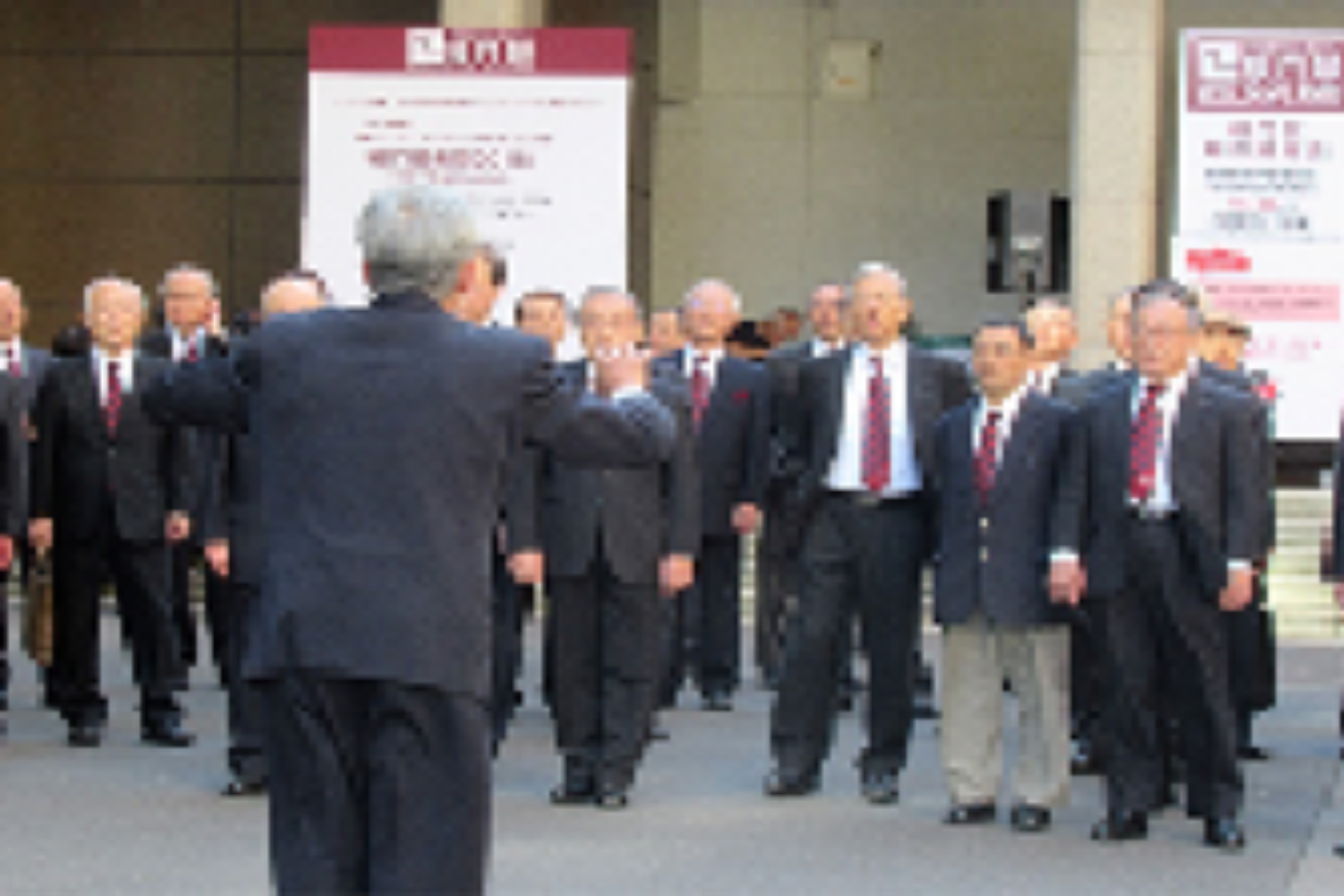GICに新加入した柳澤です。私が海外との接点を持ち、社会人になってからも技術者という職種のわりには、比較的海外とのお付き合いが多かったことの原点をお話しします。
1.大学時代での外国との接点
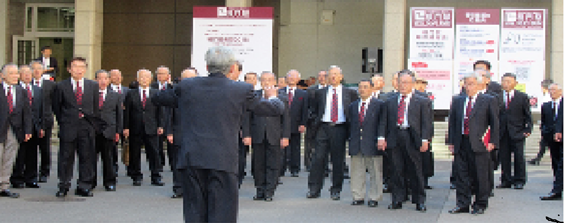
上の写真は、今年(2018年)の大学OB祭(稲門祭)でのワンショット。歌っているのは、40数年前の早稲田大学グリークラブ(男声合唱団です)で活躍していた面々。ほとんどが60代後半ですが、皆さん、まだまだ元気に歌っています。
私の海外との本格的な関りは、早稲田大学グリークラブに在籍していた時に始まります。学部4年生になる春、グリークラブは、アメリカ政府の外郭団体が主催する世界大学合唱祭に招かれました。世界16ヵ国の大学合唱団が米国に招かれ、二週間にわたって、アメリカ国内の大学を中心としたいくつかの学校を訪問し演奏会を開き、その後、ニューヨークのリンカーン・センター・コンサートホール(ニューヨークフィルハーモニーのホームコンサートホール)に集結し、一週間の合同練習の後、4日間の連続コンサートを開きました。最終ステージでは、合唱界で著名なロバート・ショウの指揮で、日本民謡を含む数曲を歌いました。合唱を愛する人間にとって、この上ない幸せな時間でした。
ニューヨークに集結する前に訪問したところはハワイ大学、エール大学、ハーバード大学やそのほかのいくつかの大学や組織で、それぞれで、演奏会を行いました。その中で、いくつもの印象に残る経験をしました。一番記憶に残り、影響を受けた経験は、ハーバード大学の寮に泊まっていた時に日本語を学んでいる学生さんと話をしたことでした。
寮には大きなラウンジがあり、そこに朝日新聞が置いてあり、久しぶりに日本の新聞をゆっくりと読んでいました。そこに、アメリカ人の学生が日本語で話しかけてきました。良い日本語会話のチャンスだと思ったのでしょう。こちらも、日本語の会話なので気楽に話しました。日常会話をしましたが、十分コミュニケーションがとれる内容でした。そこで、「何年位、日本語を勉強しているのですか?」と聞いたところ、何と一年間とのこと。
日本人が、英語を1年間習っただけで、数十分も日常会話できる人は少ないでしょう。少なくとも、当時はそうでした。アメリカ人の勤勉さと能力の高さを、初めて肌で感じた瞬間でした。
一方で、ネガティブな経験もしました。ツアーでは、飛行機とバスが主な移動手段でしたが、バスの場合、移動中にはある時間間隔で、ドライブインで休憩します。南部から東部への移動の際立寄ったドライブインで、コーヒーを飲もうと、カフェテリアに入ろうとしたら、店の係員に、「ここは白人用のカフェだ。有色人種用は建物の反対側にある。」といわれ、入場を拒否されたことで、随分と自尊心を傷つけられました。当時は、南部では、未だ未だ人種差別が激しかったのです。人種差別が、本当に人間性を否定するものであることを、肌で感じたときでした。
ふたつの主要な経験は、アメリカ社会のそれぞれの断面を肌で感じる良い経験でした。これらの経験を通じて、アメリカ社会と日本社会との差異をそれなりに感じ、アメリカ社会への興味がわきました。
2.10年後の外国との接点
それからおおよそ10年後のことです。私は、ある総合電機メーカーに勤めていましたが、会社の人材育成プログラムに手を挙げ、幸いにも社内選抜試験に合格することができ、興味があったアメリカの大学院修士コースに留学しました。アメリカで最初に設立された州立大学のひとつであり、電子工学でも評価の高いミシガン大学です。ここでは、半導体デバイスや電子回路などの勉強をしました。10年前のアメリカ音楽旅行では、少しアメリカ社会や、アメリカ人とのコミュニケーションがあった程度でしたが、今回は、どっぷりとアメリカの大学生活に浸りました。
当時、留学に必要だった英語試験のTOEFLでは、技術系の留学に必要な点数を十分に超える得点をしており、ある程度の自信をもって大学のキャンパスに降り立ったのですが・・・。
フォーマルな場所での英語は比較的通じるのですが、インフォーマルな局面ではよく分からない。ミシガンに到着して初めてレストランに一人で入ると、ウェイターからの次から次への質問攻めに困惑する羽目に。肉の焼き具合は?サラダは?ドレッシングは何にする?デザートは?紅茶かコーヒーか?
すっかり参ってしまい、それから数日間は、マクドナルドのチーズバーガーを食べることになりました。マックなら、それほど話をしなくても、チーズバーガーを買えるから。
この時初めて、言語以上に大事なのが文化、しきたりであることを認識しました。レストランに行けば、色々なことを聞かれるということを知っていることが大事だと。
ところで、当時は半導体摩擦の真っ最中。日本人、特に半導体などの電子デバイス製造業に従事している人は、日本の電子産業はアメリカより優秀という優越感を持っていた時代。私もそのような感触を抱きながら渡米しましたが、いよいよ授業が始まってみると・・・。
いました!ミシガンにも。10年前のハーバードで会った学生に勝るとも負けない秀才がいました。
米国では、学部の3年生や4年生が、大学院生向けの授業を受けることができます。その授業で異彩を放っていたのは、大学院生ではなく、学部の4年生でした。数式が並ぶ面倒くさい半導体物性の授業で、決してノートを取らず、腕組みをしながらじっと授業を聞いている。にもかかわらず、試験をすると、常に一番の成績。日本では見たことのないタイプの秀才ぶりに、一種の感動を覚えました。それまで少し馬鹿にしていたアメリカ国民を、見直しました。
冷静に考えてみると、日米のノーベル賞受賞数では、アメリカが日本より断然多く(日本の13倍以上)、文化力の差異は明らかだったとも言えると思います。ミシガン大学だけでも、ノーベル賞受賞者が7名おり、学術的な実績を残しているようです。
また、当時の米国の大学には、多くの国から留学生がいて、自然と何人かの友人ができました。アメリカ人、韓国人、アフリカ人、イラン人など。
同じ授業を受けている中では、コミュニケーションに人種間、国籍間で大きな違和感はありませんでした。もっとも、大学の中のことだけなのかもしれません。また、韓国人とは、物の捉え方や考え方が非常に近く、友達にもなったし、授業でのプロジェクトも一緒にやりました。

これらの経験が、社会人生活での海外との関りを積極的にした要因だと感じています。
字数が思ったより多くなったので、ここで一旦区切りをつけることにします。
執筆者
柳澤 俊夫